今夏のau端末は、GPSを使った新機能として「EZガイドマップ」と「災害時ナビ」を搭載している。一見するとただの新コンテンツのようにも見えるが、これまではできなかった「通信しないGPS測位」、コンテンツプロバイダーに開放された新アプリ「地図ビューアー」など、実はいくつかの新機能が盛り込まれている。
どんな新機能があり、どのように利用できるのか。ケータイのGPS機能を使ったことのない人には、ニュース記事を読んだだけでは伝わらないところだろう。GPSケータイを活用している人にとっても、従来の機能との違いがわかりにくいかもしれない。
今回はこれら2つの新サービスについて、見ていくことにしよう。
■ ダウンロード型・コンテンツプロバイダー開放・StandaloneGPS
「EZガイドマップ」は、「飲食店マップ」や「釣りマップ」といった情報を、地図の形で提供するサービスだ。その特徴の一つに、地図データをすべて端末側に保存して利用する、「ダウンロード型」というものがある。一度ダウンロードしてしまえば以後、通信する必要はない。着うたフルやEZアプリと同じような形式だ。
地図はデータフォルダ内に保存され、専用のアプリ「地図ビューアー」で表示する。この地図ビューアーはコンテンツプロバイダーに開放されていて、コンテンツプロバイダーは対応データを用意するだけで、GPSを利用したサービスを提供できる。いわばEZガイドマップは、EZwebやEZアプリと同じような「コンテンツプラットフォーム」というわけだ。
「災害時ナビ」は、地図ビューアーを使った災害時の避難支援マップだ。避難所の位置が入った全国の簡易地図が入っていて、地震などの大規模災害時に避難所を探すことを支援する。EZガイドマップのコンテンツの一つ、というとらえ方もできるが、災害時ナビの地図データは対応端末にプリセットされて無料で利用できる点が、EZガイドマップのコンテンツと異なる。また、EZガイドマップに対応しない1X端末でも、最新機種では災害時ナビ専用の地図ビューアーが搭載され、災害時ナビだけは利用できるようになっている。
地図ビューアーにはもう一つ、これまでのauのGPSケータイにはなかった特徴がある。通信をせずに位置を測定する「StandaloneGPS」と呼ばれる機能だ。これまでのGPSケータイは、GPSを起動して最初の位置測定する際に、通信して補助情報を得ることで、測位を高速化していた。逆に言うと、通信ができない場所では利用できなかった。
これに対してStandaloneGPSは、通信をせずに測位できる。通信をしない場合、最初の位置測定に時間がかかってしまうが、たとえばEZガイドマップの場合、通信できる場所では従来通りの通信を併用した測位も行なえるようになっている。
■ 「災害時ナビ」と「EZガイドマップ」におけるKDDIの狙い
|

|
|
右からKDDIの幡氏、星野氏、小林氏
|
そんなauの新しい地図サービスだが、これらを提供する意図について、開発を担当したKDDI コンシューマ事業統括本部 コンシューマ商品企画本部 auサービス企画部 ライフサポートビジネスグループリーダーの幡 容子氏、同部 ライフサポートビジネスグループ 主任の星野 世志臣氏、同部 ライフサポートビジネスグループ 課長補佐 兼 KDDI研究所 特別研究員の小林 亜令氏に聞いた。
――まずは災害時ナビのサービスのコンセプトや機能についてお聞かせください。
幡氏
GPSが使えないところがある!というユーザの声に対応しようと、まず最初に、StandaloneGPSをやろう、というところからスタートしています。通信を必要としないStandaloneGPSで何ができるか、と考えたとき、山の中などもありますが、大規模災害時にも役に立つよね、というアイディアが発端となっています。
サービスの内容としては、ユーザーが準備をしなくても使えるようにしたい、ということで、離島を含めた日本全国の広域避難所の位置、主要道路を中心とした地図をデータフォルダに納めています。ユーザー自身がデータを消さない限り、いざというときの避難を支援できるようになっています。
災害時ナビでは、EZナビウォークなどと違ってルートは検索できません。自分の位置からの方向と距離がわかるだけですが、自分が歩いてきた位置がプロットされ、歩いてきた道はわかるようになっています。また、電子コンパスを内蔵しない機種でも方角がわかるよう、太陽の位置を画面上の太陽アイコンにあわせることで、地図の方向がわかる仕組みも入っています。
|

|
|
災害時ナビ
|
――最初から入っているデータの容量はどのくらいなのですか?
幡氏
全国で3MB弱といったところです。国道や高速道路、主要県道、鉄道などが入っていますが、詳細な部分は省いてデータを小さくしています。消してしまった場合、再度ダウンロードすることも可能です。ダウンロード容量の関係から、ファイルはWIN端末では3分割、1X端末では6分割しています。
――別途販売となる「帰宅支援マップ」はどういうものなのでしょうか。
幡氏
災害時ナビよりもっと詳細な避難支援の地図を使いたい、というお客さま向けに、帰宅支援マップを提供します。たとえば自宅と勤務地など2点間を指定してもらうことで、そのあいだの詳細な帰宅支援マップがダウンロードできるというものです。
危険箇所のアイコンなどの情報は昭文社さんの書籍「震災時 帰宅支援マップ」を元にしています。書籍版だと掲載されているルートが限定されていますが、ケータイ版では自由なルートを指定できます。
|

|
|
EZガイドマップのコンテンツの1つ、「ぐるなび」によるグルメマップ
|
――次にEZガイドマップのコンセプトや機能についてお聞かせください。
星野氏
EZガイドマップは災害時ナビと同じプラットフォーム、つまり地図ビューアーを使っています。そもそもは、この地図ビューアーを一般のコンテンツプロバイダーに開放したらどうなるか、というアイディアからスタートしています。地点情報が地図上に並んでいるタウンガイドをケータイで見られるようにしよう、GPSケータイの特徴である現在位置測定もしよう、と。
ダウンロード型コンテンツということで、容量の関係から限られた範囲の地図と地点情報データしか提供できません。しかし、たとえば電車に乗っているときに目的地周辺のスポット情報を事前調査する、といった使い方もできます。また、よく行く街で、ナビは要らないけどスポット情報が欲しいな、というときにも使えます。
1.5MBという容量制限の中、コンテンツプロバイダーさんのお持ちの専門情報を自由にアレンジしていただけます。KDDIは今夏より、「ユーザーのライフタイルに寄り添う」という方針を打ち出しています。専門的な情報により、ライフスタイルに沿ったマップを提供できると考えています。
幡氏
EZナビウォークなどで、ケータイで見る地図というジャンルの素地ができました。しかし、ナビ以外の使い方を考えると、キャリアであるKDDIだけでは情報やアイディアに限界があります。そこで、コンテンツプロバイダーさんの力を借りて「地図付き情報誌」あるいは「情報付き地図」を提供しよう、というのがEZガイドマップになります。
|

|
|
「スポニチ釣りMAX」のサンプルイメージ。実際には方角を示す円などが画面上に描かれる
|
――EZガイドマップにも災害時ナビ同様に太陽アイコンが表示されていますね。あと、自分のアイコンがコンテンツごとに異なっていますが、これらは地図ビューアーの機能なのですか?
小林氏
太陽アイコンは地図ビューアーの機能です。夜間は表示されませんが、ちゃんと経度を考慮した角度に表示されます。地図上のアイコンなどはすべてコンテンツごとに異なるものを作り込めるようになっています。
幡氏
「スポニチ釣りMAX」だと自分のアイコンが釣り人になってます。コンテンツプロバイダーごとに世界を作ってくれています。
――EZガイドマップは、従来からのサービス、つまりEZナビウォークと競合してしまうのではないのでしょうか。
星野氏
EZガイドマップは専門の情報誌で、EZナビウォークは徒歩や電車の総合ナビです。EZガイドマップで下調べをして、EZナビウォークで移動をして、現地ではまたEZガイドマップを見る、といった使い分けができます。EZナビウォークのユーザーがEZガイドマップで済ませてしまう、というパターンなどもあるとは思いますが、役割も見た目も全然違うので、棲み分けできるのではないかと考えています。
また、地図ビューアーはEZナビウォークと連携することも可能です。たとえばEZガイドマップの地図上のポイントから、EZナビウォークの目的地を設定することもできます。発表済みのコンテンツはすべて、EZナビウォークとの連係機能が搭載されています。
――ユーザーがEZガイドマップのコンテンツを作ることはできないのでしょうか。
星野氏
そういった要望はもらっていますが、現状ではできません。スタート時点でそこまでは難しい、というのが正直なところです。仕様は公開していますが、KDDIによるコンテンツ審査が必要ですし、ライセンス料も必要なので、無料モデルではありません。勝手サイトが横行して地図という権利物を違法利用したコンテンツがばらまかれることも望ましくありません。
幡氏
前からGPSシステムを開放してくれ、という要望はあったのですが、やっていませんでした。しかし、EZガイドマップであれば、ほかのコンテンツプロバイダーでも利用できます。なぜ利用できるかというと、コンテンツを審査するからです。安全で個人情報が保護される、などキャリアが最低限のことを管理する仕組みにしたからこそ、開放できたと考えています。
■ 「SVG」活用で汎用性を高めた地図ビューアー
――技術的な話になりますが、地図ビューアーはKDDIが昔から研究しているSVG(Scalable Vector Graphics)の技術を使っているのですよね?
小林氏
そうです。SVGは仕様が公開されているのが最大のメリットです。コンテンツプロバイダーがEZガイドマップのコンテンツを作りたい、となったとき、SVGならば標準規格なので地図を調達しやすいですし、テキストデータなので地図上のスポット情報なども書き込みやすいです。
ただ、データ量が多くなり処理が重い、という問題もあります。それを解決するのが、KDDIが開発したXML圧縮技術の「XEUS」(ゼウス)です。SVGはXMLベースなので、XEUSで圧縮可能です。あえてSVG専用の圧縮技術にしないことで、汎用性も高めています。
――SVGのレイヤーは何枚くらい重ねられるのでしょうか。
小林氏
理論上は何枚でも重ねられます。ただ、重ねすぎると見づらかったりしますので、どのようにレイヤーを活用するかはコンテンツプロバイダーの判断次第です。災害時ナビはすごいですよ。数百枚もレイヤーを使っています。ただし、レイヤーをエリアごとに分けているので、同時に多くのレイヤーが表示されることがなく、また1つのレイヤーが狭い範囲で済むので、表示が軽くなっています。
――ちなみに、今回の新サービスはいつごろから開発を開始されたのでしょうか。
幡氏
企画側から開発のお願いをしに行ったのは、去年の10月くらいですかね。
――SVGの研究は以前からされていたとはいえ、ずいぶん短いスケジュールですね。開発された上での苦労とかはありますでしょうか。
小林氏
地図ビューアー開発の視点からですと、商用化にあたっていかに使いやすくするか、といったところですね。KDDI研究所で作っていたSVGビューアーは荒削りなもので、ユーザーインターフェイスなどは気にしていませんでした。それを商用アプリとして仕上げるにあたって、インターフェイスをどうするか、スポット検索などはどうするか、どうすれば使いやすくなるか、といった改良を施し、さらにパフォーマンスも落とさないよう開発を進めました。
――災害時ナビの方での苦労はどのようなものがありますか。
幡氏
災害時ナビは、データ集めが大変でした。なかなか集まらなくて。ある県にいたっては、データがなかったりしました。避難所にも規模レベルの分類があるのですが、各都道府県によってその分類が異なっていたりします。災害時ナビは各自治体のデータをソースにしているので、情報の収集、それを集めての見せ方は苦労したポイントです。あとはプリインストールするということで、容量を小さくすることにも苦労しましたね。
――EZガイドマップではどのような苦労がありましたか。
星野氏
EZガイドマップ的には、KDDIというよりコンテンツプロバイダーさんが苦労されたと思います。最初に声がけしたときはまだ開発ツールもできていない状態で、何ができるかを手探りで伝えていくのが大変でした。また、開発ツールも最初は使い勝手が悪かったり、途中でバージョンアップして仕様が変わったりして、KDDIへの問い合わせも多かったです。短いスケジュールで、コンテンツプロバイダーさんには、本当にがんばってもらいました。
――コンテンツプロバイダーは独自に地図を用意する必要があるようですが、たとえば地点データだけでコンテンツを作れるようにする、地図データ付きのASPサービスなどは行なわないのでしょうか。
幡氏
現状、さまざまな地図会社がありますし、地図ごとに特徴もあります。どこか1社のみと組んでやることはないと思いますし、地図ごとの特徴を考えたASPとなると、すぐにはできないかと思います。ただ、今回はコンテンツプロバイダーさんが地図会社と折衝するのが大変だったみたいなので、そこはサポートしていく考えです。
――本日はお忙しいところ、ありがとうございました。
■ EZガイドマップの使い方
EZガイドマップの使い方は、ほかのEZ系サービスとほとんど同じだ。具体的な利用方法から、サービスのイメージを紹介しよう。
まずは地図をダウンロードする。たとえばW52CAの場合、EZボタンで呼び出すメニューでからEZガイドマップのポータルサイトにアクセスして、そこでダウンロードできる。

|

|
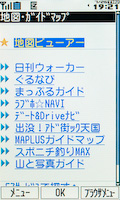
|
|
EZメニュー内のEZナビの項目から、EZナビサイトへ接続できる
|
EZナビのポータルサイト。「地図・ガイドマップ」からEZガイドマップのリストへアクセスする
|
EZガイドマップを扱うサイトのリスト。7月26日時点では対応サイトは9つだった
|
現在のところ、タウンガイドやグルメガイドといった9つのサイトが配信している。変わったところでは「スポニチ釣りMAX」や「山と写真ガイド」といったユニークなコンテンツもそろっている。こうした、「万人が必要とするわけではないだろうけど、欲しい人にはかなり嬉しい」的なコンテンツがそろっているのも、公開されたプラットフォームならではのメリットだ。
地図データは各サイトからダウンロードする。料金は、ダウンロードごとの課金と月額課金の2種類がある。金額はコンテンツによりけりだが、いまのところ無料コンテンツはないようだ(一部、無償のお試しコンテンツはある)。
たとえばぐるなびの場合、ウェブで無償提供しているコンテンツが元になっているためか、1ファイルは31円と非常に安い(通信料金がそれなりにかかるが)。ぐるなびの場合、1つのファイルが1つの繁華街を収録している。ただし大きめの繁華街の場合、分割されていることもある。ぐるなびの渋谷は北西と南東に分かれていて、南東のファイルの大きさは251KBだった。EZガイドマップの仕様上、最大1.5MBまでいけるが、だいたい1MB以下のコンテンツが主流のようだ。1MB以下でも、地図の細かさや情報の量によっては、1つの都市をカバーできるだろう。
ダウンロードした地図ファイルは、データフォルダ内の地図フォルダに保存される。地図ファイルを起動すると、まずメニューが表示され、そのメニューから地図を表示させられる。

|

|

|
|
EZガイドブックをダウンロードすると、データフォルダに「地図フォルダ」が作られる
|
地図はすべてデータフォルダ内のファイルという扱い。W52CAなどでは、デスクトップショートカットにも登録できる
|
「ぐるなび」の起動画面。地図を表示する以外にも、サイトへのリンクも入っている
|
|

|
|
「ぐるなび」の地図。地図上に「ぐ」のマークでポイント情報が表示されている
|
地図上にいくつかのアイコンが並んでいる。地図は移動と拡大縮小、回転が可能だ。十字キーでカーソル(画面中心固定)を動かし、アイコンにあわせると、アイコンの内容がポップアップ表示される。さらに決定キーを押すと、そのアイコンの詳細が表示される。
このように、「地図表示+地図上のポイント情報」というのがEZガイドマップの主な機能だ。しかし、地図表示以外の機能もある。
ぐるなびの場合、メニュー(アイコンをポイントしていない状態で決定キー)から検索もできる。ただし検索は、ジャンルを選んで絞り込み、リスト表示させるしかできない。検索後のリストはポイント地点から近い順に並んでいたりするのは、EZガイドマップならではの機能だが、ウェブ版にあるようなフリーワード検索がないのはちょっと残念だ。
店舗情報からは、ウェブ版のぐるなびに飛んだり、EZナビウォークに移動できるなど、ほかの機能との連携も可能だ。EZガイドマップでも簡単な道案内はできるが、複雑な乗換案内と道案内ならば、EZナビウォークを併用した方がよいだろう。
一度ダウンロードした地図データは、いつでも表示できる。事前に目的地周辺の地図をダウンロードしておけば、地下鉄など通信ができない環境で見ることもできる。通信が不安定になりがちな移動中でも、ストレスなしで利用できるのはありがたい。
地図上には、コンテンツが収録しているポイント情報だけでなく、アドレス帳に登録されたGPS情報も表示される。これは地図ビューアー自体の機能なので、同じく地図ビューアーを利用する「災害時ナビ」でも同様にアドレス帳のGPS情報が表示される。
このほかにも、地図ビューアーには「あしあと」というちょっと変わった機能がある。あしあとは地図上に軌跡表示されるほか、ログとしてテキストファイルに書き出せる。ログ書き出しは、いまのところあまり使い道のない機能だが、「メールでサーバーに送るとブログに軌跡入りの地図を貼り付ける」といった機能などに応用できそうだ。サードパーティによる勝手な「応用」が可能なポイントも、オープンプラットフォームならではの特徴だろう。

|

|

|
|
「ぐるなび」のポイント詳細情報の例。ぐるなびのサイト上にあるクーポンなども参照できる
|
「ぐるなび」でのサブメニュー。このサブメニューのデザインも、各コンテンツごとに異なってくる
|
検索はジャンル指定から行なう
|
■ 災害時ナビの使い方
|

|
|
災害時ナビの画面。方向を示す円などはEZガイドマップコンテンツと同じ
|
「災害時ナビ」は地図ビューアー用のファイルとして提供される。対応端末はデータフォルダに「災害時ナビ」フォルダがあり、そこに全国の地図が収録されている。WIN端末の場合、全国が3つのファイルに分割されている。それぞれ、1MB程度のファイルだ。
さすがに広範囲をカバーするだけあって、地図は大きめの道路しか収録していない。ただ、災害時はもちろん、迷子のときの最後の手段としても十分に使えそうだ。ちなみに災害時ナビの場合、StandaloneGPS限定となり、通信できる場所でも測位は高速化されないという。
災害時ナビのファイルは、消去してしまっても、サイトから再ダウンロードできる。しかしコンテンツの性質上、備えておくことに意義があるので、よほどの事情がない限り消さない方が良いだろう。
災害時ナビは、名前は「災害時」だが、当然のことながら災害時以外でも利用できる。自分の位置と最寄り駅の位置関係を見ることができるので、迷子になったときなどに便利そうだ。対応端末を持っている人は、とりあえず散歩しながらでも使ってみて、使い方に慣れて緊急時に備えておくことをお勧めしたい。
■ 対応コンテンツ・サービスの広がりに期待
EZガイドマップは、「地図付き情報誌」としてデザインされている。同じGPS連動の地図サービスではあるが、EZナビウォークは「どうやって行くか」を調べるのに特化しているのに対し、EZガイドマップは「どこに行くか」を調べることに主眼を置いているわけだ。
位置付けとしては、タウンガイドや観光ガイドブック、アウトドアガイドなどの書籍と同じ、と考えられる。自宅で現地での予定を立てるために使い、さらに現地では簡単な道案内にも使う、といった利用スタイルが想定できる。
書籍に比べると、小さな画面で見にくい、といった問題もあるが、通信やGPSと連動できるので、書籍を補完するようなサービスを提供できる。EZガイドマップは通信なしでもGPSと連動ができるため、海外の観光ガイドブックや山岳マップなど、これまでのGPSケータイではフォローできなかった分野への応用も考えられる。「災害時ナビ」も、これまでのGPSケータイではできなかった応用といえる。ちょっと使っただけでも、さまざまなアイディアが思いつける、非常に面白い機能だ。
EZガイドマップは今後、WIN端末の標準機能として搭載される見込みだ。そうなると、着うたフルやEZブックと同規模の、巨大なコンテンツプラットフォームになる。ケータイ向け電子書籍の市場は、いま急速に成長している。KDDIによれば、ナビなどの実用コンテンツも伸びているという。これまでの電子書籍では配信しにくかった地図主体のガイドブックを持つ出版社などは、EZガイドマップには注目せざるを得ないだろう。
ただ、まだまだEZガイドマップのコンテンツ数は少なく、書籍のガイドブックのように「なんでもある」という状況にはほど遠い。しかし対応端末の普及とともに、対応コンテンツも増えていくのはほぼ確実だろう。KDDIでは現在、EZガイドマップの一部を試せる「サマーガイドキャンペーン」を実施している(9月6日まで)。対応端末のユーザーは一度、試してみるのはいかがだろうか。
■ URL
EZガイドマップ
http://www.au.kddi.com/ezweb/service/ez_guidemap/
災害時ナビ
http://www.au.kddi.com/ezweb/service/saigai/
■ 関連記事
・ グルメや観光などの専用地図をダウンロード「EZガイドマップ」
・ 通信できなくても使える「災害時ナビ」
・ 「EZガイドマップ」のお試しキャンペーン
(白根 雅彦)
2007/07/27 11:18
|