|
|
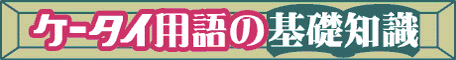
|
 |
|
第73回:WAP2.0 とは
|
 |
 |
 |
大和 哲
1968年生まれ東京都出身。88年8月、Oh!X(日本ソフトバンク)にて「我ら電脳遊戯民」を執筆。以来、パソコン誌にて初歩のプログラミング、HTML、CGI、インターネットプロトコルなどの解説記事、インターネット関連のQ&A、ゲーム分析記事などを書く。兼業テクニカルライター。ホームページはこちら。
(イラスト : 高橋哲史) |
|
この12月より発売されたauの新機種は、「WAP2.0」を採用しています。WAPとは、「Wireless Application Protocol」の略で、携帯機器から無線インターネットを使ってサーバーなどの情報にアクセスするための世界共通規格で、WAP2.0はその第2版ということになります。
au端末のインターネット接続サービスである「EZweb」は、このWAPに沿った仕様になっていたのですが、12月に発売された端末からは、版が変わって新しい「WAP2.0」対応になったというわけです。なお、WAPについては「第9回:WAP とは」をご参照ください。
WAP2.0の中身
WAP2.0は、EZwebで採用されている「WAP1.x」の後継規格にあたり、旧版と同様にWAPフォーラムによって策定され、携帯機器からインターネットへアクセスするための世界標準仕様ですが、内容的には過去のものから大幅な変更が加えられています。一番大きな変更点はとして、「インターネットで標準的に使われている技術が多く取り入れられたこと」です。
従来、WAPを利用する携帯電話では、コンテンツデータをやり取りするために、例えば「WDP(Wireless Datagram Protocol) over CDMA」などというようなWAPでしか使われない独自仕様が用いられてきました。そのため、インターネット上のサーバーを使うEZインターネットなどのために、WAPではサーバーと携帯電話の間に「ゲートウェイサーバー」を置き、この間のデータや、データをやり取りするための手順(プロトコル)を変換させていましたが、WAP2.0ではこの部分が「TCP/IP」や「HTTP」といった一般のインターネットでもよく使われている仕組みやプロトコルに置き換えられました。NTTドコモのiモードやTTNetのドットiなどでは、以前からTCP/IPやHTTPが使われていましたので、WAPもこれらのタイプの仕組みに近づいた、と言ってもいいでしょう。
ちなみにWAP2.0では、iモードの仕様が大幅に取り入れられており、WAP2.0準拠の端末とiモード端末とで、お互いにコンテンツの相互利用がしやすくなっています。また、このWAP2.0に関しては、NTTドコモも移行を検討していると発表していますので、いずれはどちらの携帯電話のコンテンツでも、WAP2.0準拠になる日がくるのかもしれません。WAP2.0はWAPとiモードをつなぐ掛け橋のように表現されることもあります。
なお、NTTドコモの次世代携帯電話サービス「FOMA」では、ネットワークの仕組みの部分ですでにWAP2.0と同じようにTCP/IPプロトコルスタックが利用されており、いずれは速やかに移行できるよう準備がされているようです。ただし、コンテンツを記述する言語については、FOMAではWML拡張に対応していないため、WAP2.0コンテンツのすべてが閲覧できるわけではありません。
話を戻すと、WAP2.0では携帯電話上で音声、カラー画像、テキストを統合したメッセージの送受信が可能な「MMS(Multimedia Messaging Service)」機能や、指定した情報がリアルタイムに通知される「WAP Push」機能、データ通信中に一般の音声通話や留守番電話が利用できる「WTA(Wireless Telephony Appication)」などの仕様も盛り込まれています。
HTMLに近くなり、コンテンツが作りやすくなった
WAP2.0では、インターネット上に置くコンテンツはW3C(World Wide Web Consortium)標準の「XHTML BASIC」を使って書かれることになりました。この部分は、以前の版のWAPでは「HDML」という独自のものだったのですが、これがオプションとなり、主役を交替しました。XHTML BASICは、これまでのHDMLより仕様的にかなりインターネットで標準的に使われているHTMLのそれに近いものになったことが特徴です。
従来のHDMLは、カードやデックというような概念から、HTMLとは少し異なる部分があるため、例えばパソコンのブラウザで見るためのWebコンテンツ制作者などにとっては、HDMLを使うEZwebでは言語体系がHTMLと大きく異なるため、サイトの作成に手間がかかってしまっていたのですが、記述言語がXHTML BASICに変わったことで、これまでよりもEZwebコンテンツがぐっと作成しやすくなるのではないかと考えられます。
なお、XHTML Basicではコンテンツの見かけ(フォントの色や大きさ、縁取りなど)を決めるような要素は、「CSS(Cascading Style Sheet)」に分離して書くことになりますので、各種端末間で共通のコンテンツを作成するような場合でも、各端末に合わせた画面表を作り込むことが可能、というような特徴があります。そのため、コンテンツを作成する場合、現在のインターネットでよくあるような、ある特定ブラウザの挙動に合わせて見かけに関する部分までHTMLで書いてしまうようなスタイルを、そのままEZWebのコンテンツ作成に持ち込めるわけではありません。なお、XHTML BASICについての詳細は、「テイク・イット・EZweb 2 【前編】XHTML Basicって何?」などをご参照ください。
また、XHTML BASICはHTMLと仕様的に近いため、iモード用HTMLなどで書かれたコンテンツもほとんど違和感なく表示できるはずです。携帯電話に内蔵されているブラウザ自体をメーカーが双方に対応するように作ることも、それほど手間にならないのではないでしょうか。実際に12月から発売されているau端末のブラウザには、Openwaveの「Openwave Mobile Browser」が使われているのですが、これはXHTML Basic、C-HTML、iモード拡張、WML拡張などの言語と、PNG、BMP、GIF、JPEGなどの画像フォーマットに対応しているので、iモード用の勝手サイトならばほとんどがそのまま利用可能なようです。
このように、XHTML BASICとこれまでのEZwebで使われていたHDMLでは、かなり仕様が変わっていますが、HDML対応の従来端末でも、XHTML BASICやiモード用HTMLで書かれたコンテンツが表示できるようになっています。これは、端末とサーバーの途中にあるコンテンツデータ変換の役割をするauのゲートウエイサーバーが、HTMLコンテンツ変換機能を持っており、XHTML BasicやC-HTMLで書かれたコンテンツを、ゲートウェイサーバー上でHDMLに変換して端末に送信するためです。
・ EZweb on the Street
http://info.ezweb.ne.jp/factory/tec/index.html
・ WAP Forum
http://www.wapforum.org/
・ 【前編】XHTML Basicって何?
・ 第9回:WAPとは
(大和 哲)
2001/12/18 13:43
|
|
|
|
|
|