|
|
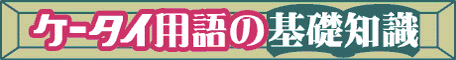
|
 |
|
第57回:ハイパートークとは
|
 |
 |
 |
大和 哲
1968年生まれ東京都出身。88年8月、Oh!X(日本ソフトバンク)にて「我ら電脳遊戯民」を執筆。以来、パソコン誌にて初歩のプログラミング、HTML、CGI、インターネットプロトコルなどの解説記事、インターネット関連のQ&A、ゲーム分析記事などを書く。兼業テクニカルライター。ホームページはこちら。
(イラスト : 高橋哲史) |
|
ハイパートークはNTTドコモの携帯電話・自動車電話の機能で、対応した携帯電話同士や固定電話をかけたときにクリアな聞き取りやすい音で通話ができる機能です。
端末では1999年11月に発売された208シリーズから、ハイパートークに対応した機能が搭載され始めました。現在では、以降502i、503i、209i、210iシリーズなどNTTドコモの800MHz帯デジタル携帯電話の新機種のほとんどと、一部の自動車電話にも搭載されています。
データが多くやりとりできるほど音は良くなる
|

|
|
ハイパートークははっきりした聞き取りやすい音で会話ができるという機能。NTTドコモの800MHz帯デジタル携帯電話の新機種のほとんどと一部の自動車電話にも搭載されている。写真は自動車電話の「デジタル・カーホンE208 HYPER」
|
デジタル携帯電話やPHSでは、音声をデジタルデータに変えて電波にのせていて、時間当たりに多くのデータを送れるほうがより鮮明な音声で通話ができます。実際には、電波にデータをのせる際にデータの圧縮なども行われるため、そのまま音質がデータ伝送スピードに比例するわけではありませんが、ほぼそれに近いくらい関係があると言っていいでしょう。
さて、デジタル携帯電話(PDC方式)では、当初、サービス開始当初、11.2kbpsのデータ転送速度(レート)が採用されていました。これが「フルレート」と呼ばれるものです。しかし、その後、携帯電話のユーザー数が爆発的に増えたため、携帯電話の周波数帯が足りなくなってくる恐れがでてきました。そのため、11.2kbpsの半分、5.6kbpsの帯域幅を使用する「ハーフレート」方式が利用されるようになりました。
しかし、ハーフレートでは時間当たりのデータが半分になってしまったわけですから、通話音質は悪化してしまいます。音声をやり取りするにはあまりにもデータが少なすぎて、データを声として再現したときにモゴモゴと言うような、聞き取りづらいものになってしまうのです。
また、通信でデータを送る場合には、データが化けることがよくあるので、誤り補正用のデータを使って、データの誤りを補いながら音声を再生するので通常はそれほど音が悪くなりにくいのですが、ハーフレートではこの補正用データも少なくなってしまうため、ノイズが起こりやすい環境ではさらに音質が悪化しやすいという問題も起きがちです。そのため、しばらく「携帯電話は音が悪い」というイメージが定着してしまったのですが、昨年からNTTドコモの携帯電話では「ハイパートーク」が採用され、音質についてはずいぶん改善されてきました。
「ハイパートーク」は、回線がそれほど混んでいないときにはフルレートで、そうでない場合はハーフレートでデータを基地局とやりとりする方式です。フルレート方式では、ひとつの周波数帯域を時間を区切って再大3台の端末で共有し、ハーフレートではこれを再大6台で共有します。ハイパートークでは使いたい周波数帯域がどの程度混雑しているのかを確認して、帯域に余裕がある時に限ってハーフレートの2倍の時間をデータ伝送に利用することができます。
またJ-PHONEのEFR方式(クリスタルボイスと呼ばれたこともあります)なども、ハーフレート、フルレートを状況に応じて利用する方式です。EFRは「Enhanced Full Rate」の略で、「高められたフルレート」という意味です。
「ハイパートーク」はNTTドコモの携帯電話が採用しているEFR方式の通話システムの商標名ですが、一般的にはこのようなタイプのフルレートの方式を指して「EFR方式」ということが多いようです。

|
|
ハイパートークは、利用できるときにはハーフレートの倍の帯域を使うことができる。さらにコーデックも改良されており、会話を非常にクリアに聞くことができるようになった
|
データ化、再生の方法を工夫してフルレートより高音質に
「ハーフレートの2倍の時間をデータ伝送に利用」ということはフルレートと同じだけデータ伝送ができる、ということです。それでは、ハイパートークの音質のよいときと元もとのフルレートでは同じ音質かという疑問が出てきます。
実は、データ伝送レートは11.2kbpsとハイパートークと元もとのフルレートは同じなのですが、音質はハイパートークのほうが良くなっています。
この秘密は「コーデック」にあります。
「コーデック」とはエンコーディングとデコーディング、つまりまたデジタルデータを音声に戻す、「コーデック」と呼ばれる作業のことです。このコーデックが改良されているために、同じ伝送レートでも音質が違っているのです。
そして、CS-ACELPはCELP方式のよく耳に聞える部分を使いやすいデータにするコードブックを使ってデータにする方法に、耳に聞える音の部分を綺麗に効率よくデータに変える、無声音の部分のデータを効率よく削るなどの新しい技術を駆使して、人間の耳の「音の聞え方」に合わせるなどして、少ないデータで効率よく人の声をデータにすることを目指して作られたアルゴリズムです。このような方式を利用しているために、特に会話に関してはフルレートよりも高音質な聞きとりやすい音質になっているのです。
また、ハイパートークでは、コーデックには音声帯域8kbps・誤り訂正符号帯域3.2kbpsのCS-ACELPが採用しています。この方式は元もとのフルレートで使われていたコーデックであるVSELP(音声帯域6.7kbps・誤り訂正符号帯域4.5kbps)よりも音声用のデータに使う部分を大きくとられていることも音質向上に貢献していると考えられます。
なお、CS-ACELPはConjugate Structure - Algebraic Code Excited Linear Prediction(共役構造代数符号励振線形予測)の略で、電気通信全般について研究や勧告を行なっている団体、国際電気通信連合(ITU: International Telecommunication Union)でG.729として勧告されている規格でもあります。
また、J-PHONEのEFRでは、ACELP(Algebraic Code Excited Linear Prediction)というコーデックが使用されています。これはGSMなどで利用されているEFRと同様のコーデックで、やはり従来のGSMのフルレートよりもさらに高音質をめざして作られたコーデックです。音声帯域6.7kbps、誤り訂正符号帯域4.5kbpsで、電波が届きにくいノイズの多い場所でも比較的再生した音声が破綻しにくいと言われています。
ハイパートークにも弱点
ハイパートーク(EFR)は音がいいことがメリットなのですが、どんな場合でもいい音質で話せるわけではない、という弱点もあります。
NTTドコモのハイパートークの場合、この機能が有効になるのは通話相手が固定電話・PHS・それにNTTドコモのハイパートーク対応の携帯電話と通話しているときだけに限られています。そのため、たとえば、本来音質がいいはずのauのcdmaOne携帯電話などと通話する場合は強制的にハーフレートになってしまい、聞き取りづらい音声となってしまいます。
また、たとえば都心の混雑時ややイベント会場などで、基地局が輻輳に近い状態になっている場合も、帯域を節約するためにハーフレートでの接続となり、このときも「モゴモゴ」というような音になってしまいます。
根本的に、800MHz帯のデジタル携帯電話は多く利用されているために混雑しやすい、という問題はどうしようもない問題です。ただし、「FOMA」などは800MHz帯とは違う周波数帯を利用しているので、ユーザーが他の規格に乗り換え出すとその状況もあるいは変わるかもしれません。
(大和 哲)
2001/08/29 00:07
|
|
|
|
|
|