|
|
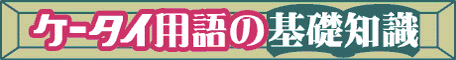
|
 |
|
第53回:General MIDI Liteとは
|
 |
 |
 |
大和 哲
1968年生まれ東京都出身。88年8月、Oh!X(日本ソフトバンク)にて「我ら電脳遊戯民」を執筆。以来、パソコン誌にて初歩のプログラミング、HTML、CGI、インターネットプロトコルなどの解説記事、インターネット関連のQ&A、ゲーム分析記事などを書く。兼業テクニカルライター。ホームページはこちら。
(イラスト : 高橋哲史) |
|
General MIDI Liteとは
今年の5月に、社団法人音楽電子事業協会 (AMEI) という団体が「General MIDI Lite(ジェネラル・ミディ・ライト 略称:GML)」という規格を発表しました。
このGeneral MIDI Liteは、携帯電話も含めた携帯端末向けの統一規格で、主に音源や楽曲ファイルのデータのありかたを決めた規格です。
「音源が一度にいくつの音を出せるのか、どのような音色が出せるのか」という音源ハードウェアの条件などが決められているほか、コンテンツの作り方のガイドラインや携帯電話に内蔵されるプレーヤーソフトの設計の仕方などのガイドラインも策定されています。
PCなどで「General MIDI」という言葉を聞いたことがある方もいるかもしれませんが、General MIDI Liteはその名前の通り、MIDI規格である「General MIDI 1.0」をベースにした規格です。携帯電話を始めとした携帯機器では、ハードウエアの制約が大きく、一般のMIDI楽器などに使われているMIDI規格であるGeneral MIDI Level1.0を適用するのが困難なため、このGMLという規格が作られました(ちなみに、General MIDI自体は1999年にさらに上位の規格の「GM2.0」が規格化されています)。
この規格は携帯電話やPDAといった小型の機器の音楽演奏用に使われる予定で、携帯電話では、この規格に準拠したデータが着信メロディや音楽コンテンツなどに使われることになるでしょう。また、音楽データの再生ができると便利だが、それほど本格的なMIDI音源を搭載できない、たとえば、情報家電機器やゲーム機、ロボットなどにも使われることになるかもしれません。
GMLのメリット
コンピュータ用の音のデータには音の情報をサンプリングしてそのままデータ化したものや、ある規則で音のデータを作っておいてそれを再生するタイプのものなどもありますが、このGMLで使われるSMF(Standard MIDI File)形式のファイルは、簡単に言うと楽譜を電子化することによって、MIDI楽器や携帯電話に「演奏」させることで音を奏でさせるタイプの音楽データです。
楽譜となるデータには音階だけではなく、それぞれのトラックに規格化された音色を割り当てることで、同じMIDIデータであれば、音階だけでなく音色も含めてほとんど違和感なくいろいろな機械で同じように音楽を再現できるようになっています。
General MIDI Liteに準拠した機器には128音色の音色が決められており、またメロディとリズムで同時発音数16音(リズムの最大は8音)を出すことができます。
General MIDI Liteに携帯電話が対応するメリットのひとつが、まずこの品質です。以前は耳障りな着信メロディしかできない機種も多くありましたが、GMLに準拠すれば、最低でもこの128音色は必ず携帯電話でも演奏に使うことができるようになります。パソコンのMIDI音源に近いような品質の良い着信メロディや音楽コンテンツが気軽に使えるようになることでしょう。
このGMLのもうひとつのメリットは互換性です。同じ音楽データをいろいろな機械(たとえば、メーカーの違う携帯電話)などでも同じデータを使いまわしすることができます。
このGMLが広く実用化されれば、この規格に準拠した携帯電話同士で着信メロディを交換したり、どの機種でも利用できる汎用的な着信メロディをパソコンで自作し、それをどの機種でも違和感なく演奏できる、などといったことも可能になることでしょう。
また、このGeneral MIDI Liteは、GM1.0規格への互換性も備えているため、GM1.0規格に対応したMIDI音源で演奏することも可能です。つまり、携帯の着信メロディをパソコンで聞く、などということもできるようになるわけです。ただし、携帯電話ではPCなどに比べると、同時発声数が少ないいため、そのままPCなどで使われるGeneral MIDI用のデータを再生することはできません。
なお、GMLのガイドラインでは、そのために、いかにしてGeneral MIDI 1.0準拠のデータからGMLデータに移行する方法なども説明されています。たとえば、「完全にユニゾンしている2つのパート(ストリングスのオクターブ・ユニゾンなど)はひとつにまとめる」「音色を重ねて表現(クリーン・ギターに軽くディストーション・ギターを重ねて音色感を出すなど)していたパートなどは、どちらかを選択する」などの方法が提示されていますので、従来のGeneral MIDI 1.0準拠のSMFからGMLへの移行を考えておられる方は一度、GMLの規格書を見ておくのもいいかもしれません。
ちなみに、GMLのコンテンツ自体はGM音源の接続されたパソコンなどのシーケンサーを利用して作ることが前提になっています。そのうえで作ったコンテンツがGM Lite規格に沿っているかを確認し、SMFとして携帯電話などに転送して再生する、という使い方が基本となるようです)。
GMLの将来
なお、このGMLに関しては、海外のMIDI規格団体であるMMA(MIDI Manufacturers Association)とも標準システムとしていく合意がなされています。ですから今後、国内だけでなく、海外の携帯電話・携帯端末でも利用される見込みですが、現在のところ、国内海外とも、対応機器の発売アナウンスなどはまだされていません。
また、規格自体の変化としては、将来的には、このGeneralMIDI Liteは著作権保護などのセキュリティ技術、電子透かし、画像やテキストとの同期再生などの規格も策定される予定になっています。
・ 音楽電子事業協会(AMEI)
http://www.amei.or.jp/
(大和 哲)
2001/07/24 00:00
|
|
|
|
|
|