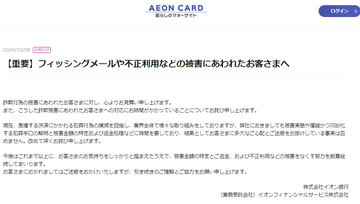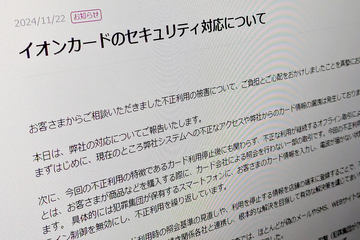ニュース
【リポート】「Revolut」がApple Payに対応、そしてFeliCa決済の今後
2025年3月3日 10:21
3月3日、決済サービスの「Revolut(レボリュート)」がApple Payに対応した。Revolutアカウントを持つユーザーは手持ちのRevolutカードをApple Walletに登録することで、アプリやWebサイト上、あるいは非接触のタッチ決済に対応したVisaカードとしてApple Payから利用できる。
日本国外で発行されているRevolutカードはすでにApple Walletに登録しての利用が可能だったが、日本国内では2020年の正式サービスイン以降もApple Pay対応が長らく行われないままだった。
今年2025年のこのタイミングになってようやくの対応となったわけだが、今回の最大のポイントは登録後のカード券面にある。
通常、日本国内で発行されるクレジットカードやデビットカードをApple Payに登録した場合、iDまたはQUICPayのマークが必ず付随し、1枚のカードでVisaなどの国際ブランドとiD/QUICPayのいずれか合わせて2種類の支払い方法が利用できる。また、日本国内では長らくVisaのブランドがApple Pay上で利用できなかったため、Apple Pay利用が可能なVisaカードであってもQUICPayのマークのみが表示され、Visaカードとしては利用できないケースもあった。
今回のRevolutのApple Pay対応は、単純に特定のクレジットカードがApple Walletに登録できるようになったという話に留まらず、長らく日本国内特有の縛りだった 「Apple Payに登録するクレジット/デビットカードには必ずiDまたはQUICPayの支払い方式が追加される」というルールが初めて緩和された ことを意味する。
RevolutのApple Pay対応が意味するもの
Revolutは、アプリ上で物理カードやバーチャルカードを簡単に発行できる点に特徴があるが、特に信頼できないECサイトなどでカード番号を入力する際に「1回のみ決済が可能なカード番号」を利用したり、必要に応じてカードを無効にしたりできるなど、柔軟な制御が可能な点で便利だ。一方で、実店舗での決済は物理カードの発行を依頼し、ICチップでもタッチ決済でも物理カード頼みという難点があったが、今回のApple Pay対応によりほとんどの場面でiPhoneさえあれば事足りるようになった。
同社は今年1月に設定ミスで日本国内でもカードのApple Pay登録を可能にしてしまう状態になっていたが、その後すぐにこの機能を無効化している。有効期間が公になっていたのは半日ほどだが、そのタイミングで米ニューヨークにいた筆者は店舗での買い物のほか、同市内の地下鉄(MTA)にも問題なくRevolutカードを登録したApple Payで乗れていることを確認している。そうした経緯もあり、Revolutによる正式発表も間近だと考えられていた。今後はApple Pay対応により、特にiPhoneユーザーの多い日本では利用機会が一気に増えるため、Revolutのサービスも改めて見直されることになるだろう。
これはセキュリティ面からもメリットがあると考える。
昨年2024年にイオンカードをApple Payとして登録する際のフローに脆弱性があり、悪意のある第三者がフィッシング等で盗んだカード番号をApple Payに登録して、その際に付与される、NTTドコモの「iD」の決済を使って買い物を行うという不正利用が相次いで話題となった。
現在は対策済みだが、iDにはカード発行会社(イシュア)ごとに店舗で決済を行ってもセンターに問い合わせが発生しない「オフライン決済」が行われる枠が設定されており、iPhoneをネットに接続しない状態で維持したまま、支払い金額が「オフライン決済」の枠内に収まる範囲で買い物を続け、本来のカード保持者には月替わりの締め日が到来するまで利用状況が報告されず、加えてリモートからカードの無効化もできないという問題があった。
根本的な問題はイオンカードの設定の脆弱性にあるが、一方でApple Payの「カード登録時に強制的にiDまたはQUICPayの紐付けが行われる」という仕様を逆手に取って不正行為が行われたこともあり、日本国内特有だった「Apple Payに登録するクレジット/デビットカードには必ずiDまたはQUICPayの支払い方式が追加される」というルールの緩和は多くのカード会社にとってメリットとなる可能性が高い。
日本の決済シーンに大きな変化をもたらす
2016年に日本にApple Payが上陸したころ、世間ではまだVisaなどの国際ブランドのタッチ決済は普及しておらず、どちらかといえばSuicaなどの交通系ICカードをはじめ、楽天Edy、iD、QUICPay、nanaco、WAONといったFeliCaベースの非接触決済の方が主流だった。
当初、Appleは日本でも諸外国同様の国際ブランドでのタッチ決済をもって普及を検討していたようだが、こうした国内の決済事情に加え、交通系IC対応によりFeliCa搭載への道筋が立ったため、最終的に「店舗決済はカードを登録時に紐付けされるiDまたはQUICPayで行う」という形での日本国内ローンチとなった。
ただ、翌年以降、MastercardやJCBといったカードの実店舗での利用が解禁され、1枚のカードで2つのブランドでの決済ができる状態となった。長らくVisaカードはApple Payでのブランドの利用を許可していなかったが、2021年5月にようやく解禁された。
情報源によれば、カードをApple Payで利用する際のiDやQUICPayへの強制紐付けをVisaでは問題視していたとされ、解禁に至った理由の1つには、強制ルールの段階的な廃止にある程度道筋が立ったためともされる。
カード会社にとっては、Apple Pay対応のために国際ブランドのみならず、iDやQUICPay側とも手数料の料率交渉をせざるを得ず、この点が負荷となって対応を諦めていたケースも少なくない。
国内の大手カード会社はほぼApple Pay対応を果たす一方で、今回のRevolutのように海外から進出してきたカード会社や、大手に比べて体力面で不利な中小のカード会社は未対応の状態が続いてきたが、これを機に一気にApple Pay対応へと流れる可能性が高い。
加えて、大手でもiDやQUICPay対応を外すケースが出てくると予想される。特に国際ブランドとiD/QUICPayを比べた際に、後者経由で決済された場合の手数料が高かった場合、収益面で不利だからだ。近年は国際ブランドのタッチ決済が利用できない店舗はどちらかといえば少数派となりつつあるため、決済ブランドを1本に絞る選択肢も当然出てくる。
こうなると、将来的なiD/QUICPayの縮小傾向が見えてくる。筆者のある情報源によれば、ドコモやJCBはこうした事態を見越して事前に対策を練り始めており、両社の間でブランド統合の可能性なども含めた協議が行われていたという。
一方で、両社ともにブランド統合やサービス縮小に向けたアクションへの抵抗勢力もあり、現在のところ目立った進展はないとされる。いずれにせよ、日本のApple Payは10年の節目を前に変化しつつあり、国内の決済事情もまた変化の波に乗らざるを得ないだろう。