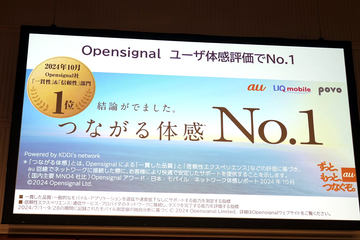藤岡雅宣の「モバイル技術百景」
携帯電話基地局の仕組みと5G通信品質の関わりは――Massive-MIMOと周波数間連携などを解説
2024年10月31日 00:00
NTTドコモが5G基地局の調達先ベンダーを変更する、あるいはKDDIが基地局の運用の仕方を工夫し優れた回線品質を実現しているなど、最近基地局関連のニュースが多く報じられています。
基地局を各地に設置していくには、非常に大きなコストが掛かり、モバイル通信事業者にとって最も大規模な資産です。
そこで、今回はあらためてモバイル通信基地局の仕組みをレビューし、基地局と5G通信品質の関係について考察します。
無線基地局の構成要素
私たちが毎日使っているスマートフォンは、基地局を介して、インターネットなどとつながっています。
個々の基地局からの電波は到達する距離に制約がありますが、人が住んでいるところやよく行き来するところで切れ目なく通信できるよう、面をカバーするように数多く設置されています。
基地局は図1に示すように、一般にベースバンド装置(BBU: Baseband Unit)と無線装置(RU: Radio Unit)及びアンテナから構成されています。モバイル通信ではインターネットからスマホへの方向を下り(Downlink)、スマホからインターネット(コアネットワーク側)の方向を上り(Uplink)とよびますが、基地局は下りと上りの両方の処理を行います。
BBU(ベースバンドユニット)は、下りではインターネットから受け取った映像や音声などのデジタルデータを無線伝送に適した形式に変換(変調)、また、上りでは逆にRU(レディオユニット)から受け取った変調信号をデジタルデータ信号に変換(復調)する非常に複雑な計算処理を行います。また、BBUは基地局同士の連携など基地局全体の運用でも重要な役割を果たします。
RUは、下りではBBUから送られてきた変調信号を電波に乗せるためのアナログ信号にしてアンテナに送る役割を、上りではアンテナが受け取ったアナログ信号から元のデジタル変調信号を取り出してBBUに送る役割を担います。
このため、BBUとの窓口にはアナログ・デジタル変換をするトランシーバー(Transceiver)があります。
アンテナはスマホとの間で直接、無線信号のやりとり、つまり下りではスマホへ電波を発射し、上りではスマホからの無線信号を受信します。
私たちがビルの屋上や鉄塔の上で見かける長い円柱状とか細長い長方形状のものがアンテナです。アンテナには細い棒状のものがあったり、屋内では天井につけられた丸い火災警報器に似た形状のものもあります。
電波は文字通り“波”であり、波に信号を乗せて送るわけですが、遠くまで届けるには大きな波を作る必要があります。
電波の大きさ、即ち振幅は波がどれだけの電力(出力)を持つかということに相当します。それで、下り方向ではRUに電力増幅器(Power Amplifier、アンプ)が組み込まれ、BBUからのデジタル信号を電波に乗せるアナログ信号に変換したあとに増幅、つまり振幅を大きくしてからアンテナに送ります。
上り方向については、スマホから大きな出力の電波を送ることはできません。また、電波は遠くへ行くほど弱くなるので、基地局アンテナはそのような弱い電波でも受けられるように優れた受信感度を持っています。
アンテナからRUへつなげるケーブルでも受信信号は減衰する(弱まる)ため、アンテナとRUの間にLNA(Low Noise Amplifier)と呼ばれる増幅器を設置することもあります。
MIMOとMassive-MIMO
基地局において、同じ帯域幅(無線周波数の広さ)でも周波数利用効率を上げて、より多くの情報量を送る手段としてMIMO(Multiple Input Multiple Output、マイモ)という技術があります。
MIMOでは複数のアンテナを同時に使うことで、情報を複数の経路に分けて送ります。たとえば、図2のように2つのアンテナを使って2つの異なる信号の流れを同時に送信すると2倍の情報量を送ることができるイメージです。
MIMOの個々の経路がそれぞれ完全に独立しているのであれば、アンテナの数だけ多くの情報量を送れますが、実際には電波は空中に発出されるので個々の経路は独立ではなく相関があります。なので、単純にアンテナの数を増やしたからといって送れる情報量がその数だけ増える訳ではありません。それでも、特に建物がたくさんある街中などではビルの反射などで個々の経路の独立性が高まり、MIMOの有効性が大きくなります。
MIMOでは、基地局アンテナを複数設けるのと同様にスマホにも複数のアンテナを組み込むことで、「2×2 MIMO」や「4×4 MIMO」として活用されています。
たとえば「2×2 MIMO」は、基地局アンテナもスマホのアンテナもそれぞれ2つあり、2つの経路で送られた電波を2つのアンテナでそれぞれ受信することを意味します。
MIMOはモバイルデータ通信が本格的に始まった3Gの時代から通信速度や通信容量を増大する手段として使われ始めました。そして4Gでは2×2 MIMOが、5Gでは4×4 MIMOや8×8 MIMOも含めて広く使われるようになり、通信容量の拡大や複数経路利用による安定した通信に役立っています。また、MIMOはWi-Fiでも利用されています。
一本のアンテナから電波を出すと、電波は全方向に同じ強さで飛んでいきます。
MIMOでは複数のアンテナを使って電波を出しますが、送信する信号の位相(電波の山や谷の位置)、タイミングを異なるアンテナ間でうまく調整し、連携することによって、特定の方向に電力を集中させ、指向性を持たせることができます。
このように 電波に指向性を持たせることを、ビームフォーミング(Beam Forming、ビーム形成) といいます。
「ビーム」は特定の方向に遠くまで届くので、基地局で利用した場合にはカバレッジ(基地局から電波が届く範囲)を拡張できます。MIMOのアンテナの数を増やしていくと、指向性をどんどん強くでき、電波をより狭い幅のビームにすることができます。そして、アンテナの数が数十、数百になるとたとえば10~20度の鋭いビームを作り、指向性をより高めることができます。
このようなMIMOを膨大な数の電波経路を持つということでMassive-MIMO(マッシブマイモ)といいます。
Massive-MIMOは、従来の4×4 MIMOや8×8 MIMOよりも電波の到達距離が大きく、その分、カバレッジが広くなります。電波は周波数が高くなると飛びが悪くなるので、Massive-MIMOは5G専用に割り当てられたような高い周波数で、できるだけ大きなカバレッジを実現したいときに有効です。
Massive-MIMOではビームをスマホに向けて送り、逆にスマホが無い方向には電波を発出しないので電波を無駄なく利用できます。また、Massive-MIMOではMU(マルチユーザー)-MIMOと言う、同時に複数のビームを形成してそれぞれ異なるスマホとの通信に利用することも可能です。このように、Massive-MIMOを用いると電波を効率良く利用して、基地局全体としての通信容量を拡大することができます。
Massive-MIMO無線装置
図3にMassive-MIMOアンテナのイメージと製品例を示します。Massive-MIMOでは個々のアンテナは実際には小さなアンテナ素子として実装され、アンテナ素子を縦横に並べて全体としてMassive-MIMOのアンテナ(群)を形成します。
アンテナ素子の長さは電波の効率的な送受信を実現するため、使う電波の波長(波の頂点間の距離)の1/2とします。たとえば5Gで使われる4GHz帯の周波数だと波長が7.5cm程度なので、アンテナ素子の長さは3.75cm程度となります。
Massive-MIMOのアンテナは、実際には図1で説明した基地局の構成における無線装置(RU)と一体化して実装しています。一般に個々のアンテナ素子ごとにアンプが併設されており、アンプとアンテナとの間の伝送に伴う信号の減衰や雑音発生を抑制しています。また、BBUとの間のデジタル信号とアナログ信号を変換するトランシーバーもアンプに併設しています。
Massive-MIMO用の装置は、商用導入初期時は64アンテナ素子の製品では、たとえば高さ1m、幅50cm、重量50kgなど扱いにくく、設置できる場所が限定されていました。しかし、現在は装置の小型・軽量化が進み、たとえば32アンテナ素子で15kg以下の重量の製品も商用化されており、設置場所の自由度も高まっています。
なお、Massive-MIMOは、基地局側では多数のアンテナ素子を利用して電波の送信、受信を行いますが一般にスマホ(端末)側ではスペースの制約もあり、2つ、4といったアンテナ素子しか持っていません。
そのため、Massive-MIMOのスペックは基地局側のアンテナ素子数を用いて「32T32R(送信側も受信側も32素子)」とか「64T64R」と表現します。TとRは、それぞれTransmit(送信)とReceive(受信)の略です。
世界の5G基地局の動向
日本では、4G LTEで既にソフトバンクが3.5GHz帯などでMassive-MIMOを備えた基地局を一部導入しました。しかし、5Gとして割り当てられている3.7GHz帯や4.5GHz帯などのいわゆるSub-6(サブシックス、6GHz以下の5G専用周波数)では、無線装置の重量や大きさ、設置基準などの問題もありMassive-MIMOの導入があまり進んでいません。
一方で海外に目を向けると、5Gを展開している世界各国でサブ6の基地局の70~100%で、32アンテナ素子や64素子(2つとか4つの素子を束ねて一つの組としている場合もあり、その場合は32組や64組)を用いるMassive-MIMOが導入されています。これにより、高速通信が可能な5Gのカバレッジを大きくし、通信トラフィックの増大に対処しています。
今般、ドコモが5G基地局の調達先ベンダーを変更することにした背景には、Massive-MIMOを有する基地局を導入して5Gのカバレッジやデータ通信容量を一気に向上させてユーザーの体感品質を改善していこうという狙いがあると思われます。条件にもよりますが、4×4 MIMOに比較して32アンテナ素子のMassive-MIMOは下りで2~3倍程度、上りで1.5~2倍程度の通信容量を持つという報告もあります。
周波数間の連携
モバイルネットワークにおいては4Gまでは700~900MHzのプラチナバンド、および1.5/1.7/2/2.5/3.5GHz帯などの周波数が利用されてきました。そして、5Gで3.7/4.5GHz帯と28GHz帯などが追加されています。
このように多様な周波数を補完的に利用しながらユーザーに高品質のモバイル通信サービスを提供しています。全体として、低い周波数でカバレッジを拡げながら、より高い周波数で通信速度を高めるという見方ができます。
実際、4Gでは各事業者に10/20/40MHz単位でモバイル通信の周波数が割り当てられてきましたが、5Gのサブ6は100MHz単位、28GHz帯は400MHz単位で割り当てられており、一般に周波数が高いほど広い帯域を利用できます。
通信速度はおおむね利用する周波数帯域の幅に比例して大きくできるので、より広い帯域幅が使える高い周波数が通信速度の押上げに寄与します。
5Gでも、異なる周波数を補完的に利用することが有効です。3.7/4.5GHz帯のサブ6だけで面的に連続したカバレッジを早い段階で実現することは難しいため、5Gのカバレッジを確保するために従来の4G周波数の一部を補完的に利用することがひとつの手段になります。従来の4G周波数を5Gとして転用できればサブ6のカバレッジが無いところも5Gが連続的に利用でき、スマホにも「5G」と連続的に表示されます。
たとえばKDDIは「デュアル5G」と呼んで、「4G転用周波数5G」で5Gの面的な広いカバレッジを作った上にサブ6の5Gカバレッジを被せる方策を採っています。基地局からの距離が離れるなど、サブ6の電波が弱くなったところ(フリンジ)ではサブ6の無線は開放して4G転用周波数5G(以下、転用5G)のみを利用するようにすることで、ユーザーは連続して5Gを利用できるとしています。
一方でサブ6基地局のフリンジで転用5Gのカバレッジがない場合に、5G接続を維持するためにサブ6の無線接続を引き続き利用しようとすると、ユーザーが満足する品質が提供できなくなる可能性があります。この問題は、できるだけ5G接続を維持する方策を採る場合に生じます。この場合、5Gを優先せずサブ6の無線は早めに開放して4Gを利用するのが得策かも知れませんが、スマホには「4G」と表示されます。
サブ6基地局のカバレッジ拡大
さて、異なる周波数を束ねて一つのパイプとして利用することをキャリアアグリゲーション(CA: Carrier Aggregation、キャリアというのは『搬送波』のこと。情報を運ぶ入れものという意味)と言います。基地局とスマホの間で複数の周波数が利用可能なときに、CAにより無線帯域を束ねて効率良く利用します。
実は、このCAには優れた効用があります。
図4に示すように、サブ6と転用5Gの基地局が同じサイトにあると想定した場合、各周波数を個別に利用した場合のカバレッジは実線で示した通りです。一方で、両周波数をCAで束ねた場合には、サブ6のカバレッジが点線で示したように拡大する可能性があります。
これは、転用5Gを主キャリア、サブ6を副キャリアとしてCAで束ねた場合、サブ6副キャリアにおけるスマホから基地局向けの「キャリア内制御信号」を転用5Gの主キャリアを用いて送ることができるからです。制御信号というのは、たとえばデータを送ったときに問題無く受信できたかどうかを受け側から送り側に知らせる信号です。この制御信号が正しく受け取られないと、通信が成立しません。
サブ6を単独で使う場合には、データも制御信号もそのサブ6キャリアを使って送ります。一方、CAではサブ6でデータを送り、それに関わる制御信号を転用5Gで送ることが可能です。転用5Gのほうが一般に電波品質が良い状態で受け側に届くので、より高い確率で正しく受け取られます。データは受け側に届けられたけれど、受信確認を送り側に伝えらないので結局データ送信が失敗するということがなくなるわけです。
基地局はスマホよりも大きな出力で電波を発信することが可能です。なので、サブ6を単独で使っている場合には、基地局から少し離れた場所では基地局から送られたデータはスマホで正しく受け取られていても、スマホからの正しく受け取られたという確認の制御信号が基地局には正しく届かないことがあり得ます。
図4のサブ6カバレッジの実線と点線の間のエリアでそのような現象が起こります。CAを用いた場合には、スマホから転用5Gを使って確認の制御信号を送ればそれが基地局に正しく届く確率が高まります。従って、CAによりそのようなエリアまでサブ6のサービスエリアとして使えるようになります。このようにCAはサブ6の実質的なカバレッジを拡大させる効果があります。
基地局間の連携
CAなど周波数間の連携を実現するためには、異なる周波数の基地局同士の連携が必要となります。
基地局間連携のためには異なる基地局のBBU間で信号をやりとりする必要があるのですが、その手順が必ずしも基地局ベンダー間で統一されていません。つまり、同じベンダーの基地局同士であれば連携できても、異なるベンダー同士では連携できない可能性があります。
業界団体であるO-RAN Allianceなどでは、特に5Gにおけるこのようなマルチベンダーの相互接続性を担保するための標準化を進めていますが、未だ道半ばであり実用化のレベルには達していないのが現状です。
なので、基地局の調達先ベンダーを代える場合など、基地局間連携の観点も含めて十分に長期的なネットワーク展開方策を考えておく必要があります。
5Gスタンドアローンへの進化
5Gの面的で連続的なカバレッジは、5Gスタンドアローン(SA: Standalone)への進化においても非常に重要です。
現在、日本で商用提供されている5Gは、4G基地局の存在を前提に5Gを実現する非スタンドアローン(NSA:Non-Standalone)構成が主となっています。図5(1)に示すように、NSA構成では4G基地局群の中に5Gの基地局が追加実装される形になっています。
一方で、図5(2)に示すようにSA構成は4G基地局の存在を前提とせず、5G基地局のみから構成されます。
SA構成はネットワーク全体が単純化されると同時に無線接続を効率良く利用するように設計されているため、通信の遅延(基地局とスマホの間でデータの送受に掛かる時間)を短くしたり、通信速度を大きくしたりするなど全体の通信性能を向上できます。
また、SA構成はアプリケーションに応じて必要なネットワーク機能を切り出して利用するネットワークスライシングの導入により、さまざまな産業界での利用が期待されます。
サービス品質保証などの高度な機能も提供できることから、5Gの利用がスマホだけではなく装置や車両、機械などの多様なデバイスに広がり新たな需要を生み出すことになります。
世界的に初期の5Gはその導入のしやすさからNSA構成となっていますが、上記のようなメリットがあるので、5Gのカバレッジが広がってくるとSA構成を導入する方向です。
日本でも、各モバイル通信事業者が一部の地域や特定の用途にSA構成を導入しており、徐々に対象エリアやユースケースを拡大しています。SA構成の広がりにより、いよいよ本格的な5Gの時代が訪れることが期待されます。
SA構成を前提として、広域で、あるいは移動しながら利用するサービスについては、面的に連続してシームレスに提供されることが望まれます。
そのためには、5Gの広域でのカバレッジを確保する必要があります。なので、SAへの更なる進化に向けて、サブ6だけでシームレスなカバレッジが担保できない場合には転用5Gも利用して面的なカバレッジを担保することが期待されるわけです。
おわりに
スタンドアローン(SA)構成を含め5Gが本格化するに従い、モバイル通信事業者間での5Gの競争が、より本格化すると考えられます。
この競争では、5G基地局の数量や性能、密な基地局間連携が大きな役割を果たします。
5Gはサービス開始から4年半を経過して、期待よりは遅かったかもしれませんがいよいよ本格的な需要期になると想定されます。基地局の拡充を含めて、ネットワークの進化に期待したいと思います。
一方、最近「エッジAI」として、データセンターだけではなく、さまざまな場所にAIのサーバーを設けて、いろんな用途にAIを使っていこうという機運が盛り上がっています。
たとえば、全国に配備されている基地局の余っている処理能力をAI処理に使うことができれば、増大するローカルなAI処理需要を取り込むことができる可能性があります。このような観点から、今後基地局の役割が大きく変わっていく可能性もあります。