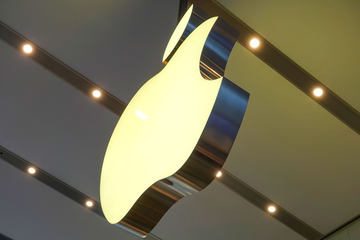法林岳之の「週刊モバイルCATCH UP」

KDDIがGoogleメッセージを選んだワケ~『+メッセージ』はどうなるの?
2024年5月21日 00:00
先週、KDDIから「メッセージサービスの魅力向上に向け Googleメッセージを採用」というニュースリリースが発表された。国内ではLINEが広く利用される一方、各携帯電話会社が『+メッセージ』を提供している。
なぜ、KDDIはこのタイミングで、メッセージサービスの新しい方針を打ち出したのだろうか。携帯電話やスマートフォンにおけるメッセージングサービスの今後について、考えてみよう。
コミュニケーションに欠かせないメッセージングサービス
友だちや家族、同僚、取引先など、誰かとコミュニケーションを取る手段と言えば、何だろうか。かつては圧倒的に『音声通話』だったが、インターネットが普及したことでメールの利用が増え、スマートフォン時代はテキストメッセージによるコミュニケーション、つまり、『メッセージングサービス』が広く利用されるようになってきた。
スマートフォンで利用されるメッセージングサービスには、SNSなども含めると、多様なサービスが提供されているが、国内の携帯電話サービスでは、NTTドコモ、au、ソフトバンクが2018年から「+メッセージ」を提供している。
それまでのSMS(ショートメッセージサービス)を拡張したRCS(リッチコミュニケーションサービス)規格に準拠したサービスで、携帯電話番号を使うことで、文字メッセージだけでなく、写真やスタンプなどもやり取りができる。ちなみに、RCSはGSMAで標準化された国際標準規格で、すでに世界中の通信事業者が採用し、対応端末や採用サービスが拡大している。
2018年のサービス発表は、各携帯電話会社が共同で記者会見を開き、サービス内容を解説するという異例の取り組みだったが、その背景にはかつてのケータイ時代、各社がそれぞれの独自仕様のメッセージングサービスを提供したものの、同じ携帯電話会社のユーザー同士しかやり取りができなかったため、ほとんど普及しなかったことの反省が活かされている。
時代の主流はスマートフォンへ移行したが、RCSという国際標準規格に準拠した「+メッセージ」を携帯電話会社が提供する標準的なメッセージングサービスとして、育てていきたいと考えたわけだ。
「+メッセージ」は当初、3社のスマートフォン向けのみで提供され、その後、UQモバイルやワイモバイル、LINEMO、povoなど、各社の別ブランド向けにも順次展開。現在は3社のネットワークを利用したMVNOでも利用できる環境が整っている。
端末についてもAndroidスマートフォンからスタートし、iPhoneやiPadでも利用可能になり、G'zOne TYPE-XXなど、一部のLinuxベース(Androidベース)のフィーチャーフォン向けにもアプリが提供され、今年2月には利用者数(回線数)が4000万人を超えたことが報じられた。
広く利用されてきた「LINE」だが……
一方、同様のメッセージングサービスとして、国内を中心に広く利用されているのかLINEヤフーが提供する「LINE」だ。2011年から国内でのサービスの提供が開始され、手軽さとスタンプなどの楽しさから利用が拡大し、モバイル社会研究所(NTTドコモ)の統計によれば、2024年1月現在、SNSの利用率ではトップの85%を記録している。
しかし、その一方で「LINE」はこれまでさまざまな問題が指摘されてきた。たとえば、初期登録時に端末内の連絡先とマッチングを取り、自動的に友だちに追加できるようにしたことで、意図しない相手が登録されてしまったり、当初はアカウント作成に年齢制限がなく、未成年者がトラブルに巻き込まれたりした。
スマートフォンではつい最近まで、プラットフォーム間でのトークの引き継ぎができなかったり、Linuxベース(Androidベース)のフィーチャーフォン向けアプリの開発と提供を一方的にやめてしまうなど、サポート面にも不安を残している。
これらに加え、ここ数年は度重なる情報漏えいやセキュリティ対策の不備が指摘され、総務省から二度に渡る行政指導を受けるなど、サービスとしての信頼性や安全性が疑問視されている。
利用者数の多さから、災害時の情報提供や自治体サービスの情報発信にLINEを使うケースもあるが、情報漏えいやセキュリティ面のトラブルなどから、「公的なサービスにLINEを使うべきではない」という指摘も少なくない。
NTTドコモ、au、ソフトバンクが「+メッセージ」の提供を開始し、普及を推し進めてきた背景には、メッセージングサービスとして、「LINE」に対抗する意味合いが強かった。
ただ、2019年にソフトバンク傘下でYahoo!を提供するZホールディングスがLINEとの経営統合に合意し、2021年に経営を統合したため、各社の足並みが乱れたとも言われる。KDDは当初から「+メッセージ」に注力しており、さまざまな公式アカウントを用意したり、「プラメポータル」や「プラメクイズ」などのコンテンツサービスなど積極的に拡充してきたのに対し、NTTドコモやソフトバンクはサービスこそ、提供するものの、当初はやや様子見の感があった。
しかし、NTTドコモもKDDIに追随する形で「ドコモ災害対策」などの自社コンテンツの配信を開始し、ソフトバンクもワイモバイル向けの[Y!mobileメール]アプリで、「Y!mobileメール」や「Yahoo!メール」、「+メッセージ」を一括で扱えるようにするなど、少しずつユーザーの利用環境を整えてきた印象だ。
こうした地道が活動の効果もあってか、前述のように「+メッセージ」の利用者数が4000万人を超え、「LINE」に対する行政指導の影響も加わり、徐々に携帯電話サービスのメッセージングサービスとして定着する兆しを見せ始めていた。
KDDIが「Googleメッセージ採用」を表明
そんな中、先週、KDDIから「メッセージサービスの魅力向上に向け Googleメッセージを採用」というニュースリリースが発表された。
Googleが提供する「Googleメッセージ」は、「+メッセージ」と同じく、RCS規格に準拠したもので、エンドツーエンドの暗号化が可能になり、文字メッセージだけでなく、写真や動画の送受信、1対1やグループでのチャット、既読/未読の確認などの機能も搭載される。
Googleが発表した内容では、「今後、KDDIが販売するAndroid端末にGoogleメッセージを標準アプリとして採用していくことをKDDIが発表されました。日本においてOSに関わらずスマートフォンを利用する全ての方が、便利な最新のテキストメッセージを安心してお使いいただけるよう、今後もKDDIをはじめ、日本のパートナーと一緒に取り組んでまいります」と記されており、GoogleとKDDIがRCS規格の準拠したGoogleメッセージを積極的に推し進めていくことが示されている。
これまで業界の先頭に立って、「+メッセージ」を推し進めてきたKDDIがいきなり手のひらを返したかのような方針転換にも受け取れる内容で、一部のユーザーからは「+メッセージ、なくなるの?」といった戸惑いの声も挙がっている。
こうしたKDDIとGoogleの動きの背景にあるのは、アップルがRCSに対応したメッセージングサービスを準備しているからだと見る向きもある。アップルはこれまで独自仕様のメッセージングサービスとして、「iMessage」を展開してきた。
ここでは「iMessage」について詳しく説明しないが、「iMessage」はApple IDに紐付いた独自規格のメッセージングサービスで、アップル以外のプラットフォームでは利用できない。
こうした状況に対し、すでにRCS規格準拠のサービスが整いつつある各社からは、「iPhoneが対応しないから、RCSが普及しない」といった声が挙がっていた。2022年には業を煮やしたGoogleがAppleにRCS対応を求めるサイトを公開するなど、業界全体を挙げて、Appleの対応の遅れを指摘していたが、昨年11月、ようやくアップルはこれまでiPhoneで対応してこなかったRCSを2024年にサポートすることを明らかにした。
おそらく、今年6月に開催されるWWDCで触れられる次期iOS/iPad OSに実装されると見られ、今年中にも対応サービスが開始される見込みだ。こうしたアップルのRCS規格対応サービスへの取り組みを控えているため、GoogleとKDDIがいち早く「Googleメッセージ採用」を表明することで、業界標準の位置付けを固めようとしたとする指摘もある。
「AI」によって大きく変わるメッセージングサービス
確かに、スマートフォンの市場において、約半分を占めるアップルのRCS対応への取り組みは気になるが、実は今回のKDDIとGoogleの発表には、もうひとつ大事なテーマが掲げられている。それは言うまでもなく、「AI」の利用だろう。
KDDIのニュースリリースの中では、「今後、AIなどの技術を活用し、メッセージサービスのユーザーエクスペリエンス向上を目指していきます。」と書かれているが、おそらく今後のスマートフォンで利用するコミュニケーションにおいて、「AI」が大きな変革をもたらすことは確実視されている。
たとえば、今年4月に国内向けに発売されたサムスンの「Galaxy S24」シリーズでは、新たに搭載された「Galaxy AI」により、外国語を通訳しながら音声通話ができる「リアルタイム通訳(ライブ翻訳)」が注目を集めた。
この機能はユーザーの音声を認識し、テキスト化し、言語間で翻訳し、相手の言語で音声を発信するというしくみで動作している。つまり、[電話]アプリに、「Galaxy AI」による音声認識やテキスト化などの機能を組み込むことによって、実現しているわけだ。
「Galaxy AI」を利用した機能として、異なる言語を利用する相手と外国語で翻訳しながらメッセージをやり取りできる「チャットの翻訳」も提供されている。
これはサムスンが独自に提供する「Samsungキーボード」によって、入力した日本語を外国語に翻訳して、相手に送信し、相手から送られてきた外国語のメッセージを翻訳し、日本語として表示している。「チャットの翻訳」で利用できるアプリは、「+メッセージ」だけでなく、「LINE」や「Instagram」でも利用できる。
また、端末は未発売だが、先般、発表されたシャープの「AQUOS R9」では、生成AIを活かした機能のひとつとして、「代わりに聞いときます」という機能が搭載される。電話がかかってきたとき、着信に応答するのではなく、生成AIに代わりに応答してもらい、メッセージの内容をAIで要約するという機能になるという。
言わば、「要約機能付きAI留守番電話(伝言メモ)」のようなものだが、今後、AIの性能が向上すれば、映画「アイアンマン」の人工知能「ジャービス(J.A.R.V.I.S)」よろしく、まるで秘書や執事のように、さまざまな着信に応対して、要件をまとめてくれる世界が実現できるかもしれない(笑)。
こうしたサムスンやシャープの対応を見てもわかるように、スマートフォンや携帯電話のもっともベーシックな機能である音声通話やメッセージングサービスは、今後、AIによって、大きく変わってくる。
サムスンは「Galaxy S24」シリーズの[電話]アプリや「Samsungキーボード」などに、こうした翻訳や要約などの機能を実現する「Galaxy AI」を組み込むことができたが、各携帯電話会社が提供する「+メッセージ」などのメッセージングサービスに翻訳や通訳、要約などのAIを組み込むとなると、[+メッセージ]アプリにAIに対応するAPIなどを定義するなど、かなりの大工事を強いられる可能性が高い。
また、Googleとしては「Google I/O」でも取り上げられたAI関連の機能やサービスをAndroidプラットフォームに順次、組み込んでいくため、同社が提供する数々のアプリもAIに対応する仕様に変更していく。
なかでも音声通話とメッセージングサービスは、ユーザーにとって、もっとも身近なものであり、サムスンやシャープの例を見てもわかるように、実現しやすい機能が多く考えられる。こうしたことを踏まえ、Googleが提供するサービスをいち早く利用できるように、KDDIは「Googleメッセージ」への対応をうたったわけだ。
では、「+メッセージ」がどうなるのか。現時点で、KDDIはニュースリリース内で「Android端末へのGoogleメッセージアプリの採用時期については、改めてお知らせします」と説明しており、いつ「Googleメッセージ」が提供されるのかは明らかになっていない。
KDDIの担当者によれば、「+メッセージ」をやめるのではなく、 「Googleメッセージ」に対応するというのがニュースリリースの内容 。2つのサービスをはじめ、他のRCSサービスとの互換性や連携を確認しながら、RCSサービスの提供を検討していくとしている。現時点で「Googleメッセージ」の仕様や実装を調査中のため、こうした回答になるようだ。
これまで提供してきた「+メッセージ」がいきなり終了するようなことはないだろうが、今後、スマートフォンではAI実装のために、標準アプリの仕様や扱いなどが変更されることがかなり増えてくることが予想される。
ユーザーとしては各社のサービスが業界の動向に合わせ、どのようにアップデートされ、私たちの利用環境にどのような変革がもたらされるのかをしっかりとチェックするように心がけたい。