ケータイ用語の基礎知識
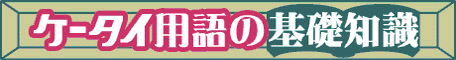
第860回:オーバークロック とは
2018年6月13日 12:08
クロック周波数を定格値より上げる
「オーバークロック」とは、ICやLSIなどの動作クロック周波数を定格値より上げて動作させることを指す言葉です。「クロックアップ」と言われることもあります。
パソコンでは、ユーザーが自己責任で行うチューンアップの対象のひとつとして取り上げられることが多い用語です。
スマートフォンでは最近、ASUSが発表したゲーマー向けスマートフォン「ROG Phone」が、搭載するチップセット「Snapdragon 845」の定格2.8GHzに対して、最大2.96GHzのオーバークロックを行えると、製品発表会で紹介されました。
クロックとは何か
“クロック”とは、簡単に言うと、処理のタイミングを合わせるための信号のことです。CPUはタイミングに合わせてメモリーから値を読んだり、計算をしたりします。必ずしもひとつの信号タイミングが1つの処理というわけではなく、4クロックでひとつの処理、8クロックでひとつの処理などと言うこともあります。
信号が一秒間に何回、LSIに供給されるか、数値で示したものをクロック周波数と呼びます。単位はHzです。1GHzであれば一秒間に10億回のタイミングでクロックが供給されている、ということになるわけです。
あるコンピューターで、たとえば2.8GHzで14億個の処理ができるようなプログラムであれば、2.96GHzを供給すれば14.53億個の処理ができるように性能がアップする、というわけです。
オーバークロックの弊害
オーバークロックによって計算機の性能は上がります。が、このチューニングにはいくつかの弊害があり、一般的にはパソコンやスマートフォンのメーカーは行いません。弊害として代表的なものは、発熱と損傷の可能性でしょう。
ただでさえ動作する際には発熱するコンピューターですが、オーバークロックで動作するチップセットは、一般には動作周波数を上げた分だけ供給電圧も上げることが多くなります。つまり、オーバークロックすれば、さらに熱くなりやすいわけです。
その熱を逃がし損ねてしまうと、回路上の部品が熱で損傷してしまう可能性もあります。そのためオーバークロックを行う際には、CPUを含めて回路全体を冷やさなけれなりません。一般的に、CPUを含んだチップセットなどは定格の周波数で動作することを前提に設計されています。それを超えるということは、チップセットメーカーの想定外の使い方をすることになるわけです。
最近では、チップセットの温度が一定以上になると、クロック信号の供給を下げたり、供給電圧も強制的に下げたりといった動作をするCPUも多くあり、限界を超えるようなオーバークロックも機械にとって致命的になるケースは少なくなりました。
しかし、それでも定格以上(マージン内)で動いていることに変わりはないわけで、メーカー自らがオーバークロックを行って出荷される「ROG Phone」には多くの人が驚かされるわけです。ROG Phoneはゲーマー向けブランドを冠したスマートフォンであり、高い処理能力を求めるユーザー層に向けた仕掛けと言えそうです。
