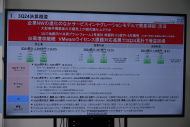ニュース
IIJの第3四半期決算は増収増益――モバイル市場は競争激化も“新ギガプラン”で顧客満足度向上、鈴木会長はAI活用で現場復帰
2025年2月7日 18:18
インターネットイニシアティブ(IIJ)は7日、2025年3月期第3四半期決算を発表した。
連結決算は、売上が2293億1000万円(前年同期比+14.0%)、営業利益が207億500万円(同2.1%)、純利益が137億8600万円(+6.2%)だった。モバイルを除いたネットワークサービスとモバイル事業で高い売上となったことに加え、システムインテグレーター領域では、更新需要が活発で増収に貢献。それぞれの粗利も前年同期比で15億円弱の増加となり、増益を牽引した。
法人向けは堅調、個人向けは競争激化で回線減
法人向けのインターネット接続サービスは、トラフィックが増加傾向であり、帯域保証型の専用線サービスでは、前年比+7.3%の128.1億円、法人IoT向けの法人モバイルでは+12.1%の112.6億円の売上を達成。ほかのMVNO向けにサービスを販売するMVNEは、法人向けモバイルのうち+7.9%の85.0億円とこちらも堅調に推移している。
個人向けの接続サービスの売上は、+6.3%の198.8億円。うち、モバイルサービス「IIJmio」は+7.1%の173.8億円となった。市場環境は安定しているとするほか、端末の拡充やeSIMなどの積極展開を継続しているという。
モバイルカテゴリーの具体的な数字を見てみると、回線数は法人向けで300.0万回線(前期比+27.6万回線)、MVNE向けで123.1万回線(+2.1万回線)、IIJmioで128.4万回線(-1.0万回線)。
法人向けでは、ネットワークカメラやGPSデバイス、車載器接続など、既存顧客の拡充に加え新規案件の獲得で伸長、MVNEでも売上、回線数ともに成長しており、顧客数も増加している。
コンシューマー向けでは、IIJmioではギガプランの回線数自体は増えている(108.5万回線)ものの、全体の回線数では、今年度初めて純減となった。
代表取締役社長の勝栄二郎氏は、回線数減少の理由を「競争環境が厳しいこと、我々としてもキャンペーンを少し控えていたということがある。そういうこと(回線数の減少)は時々起こるものだと思っている」と分析。3月に改定される料金プラン「ギガプラン」の狙いについては、“5GBを中心とした低容量帯の強化”と“大容量プランでデータ量の増量を実施”を実施。勝氏は「競争力があるものになった」との考えを示した上で「ユーザーの満足度が今でも“ナンバーワン”だと思っているが、これをさらに上げること、長期利用していただけるようにしたい」とその狙いを説明した。
4月に社長交代
既報のとおり、同社の社長人事について、3月31日で現社長の勝氏は退任し、4月1日に代表取締役社長 Co-CEO&COOとして谷脇康彦氏が就任する。
勝氏は「時には温かい言葉、厳しい言葉もいただきながら12年間なんとかやり遂げられた」とコメント。自身が達成できたことを問われた勝氏は「たいしたことはしていない」と前置きしたうえで「若手、中堅社員が全社的な課題に対してプロジェクトチームを結成し、さまざまな課題に取り組める体制とした」ことと説明。
谷脇新社長について「情報通信に知見が深く、総務省の通信部門でもトップでマネジメント能力も高い」とその手腕を評価。中期経営計画も新社長がリードしてやってもらえるとエールを送った。
鈴木会長「バックオフィスをAIで効率化していく時代」
説明会で代表取締役会長の鈴木幸一氏は、先頃“室長”という肩書きで現場に復帰したことを明かし、「急速な発展をしていこうとして、さまざまなサービスを作ってきた」と1999年の米国ナスダック上場時を振り返る。この際の“社長兼運用部長”としての役割ぶりに現場に復帰したとコメント。
その際は、ほとんどがエンジニアで、経理などを担当するバックオフィスの人員はあまりいなかったが、会社が発展してきた現在、多くの人員が集まってきたと指摘。今後会社が発展していくためには、このバックオフィスをいかに効率化していくべきかが重要だと指摘。近年のAIによって効率化が実現できるのではないかとし「自分が室長もやれば決裁も早くなる」と自らが室長となって旗振り役を買って出たと話す。
AIを気軽に使えるようにすることで、効率的な経営でたくさんのサービスを導入できると“大きなテーマ”だと鈴木氏はその重要性を説明する。鈴木氏は「決して社長や会長を辞めたわけではない」と釘を刺すが、「来期には、方向性や成果を伝えられるのではないかと思う」と、進捗をアピールした。
「AIによって“余剰人員”ができるのでは?」という問いには「全くそうは思わない」と話す鈴木氏。続けて「いつまでも人や経済が成長しないのであれば余剰人員が発生するだろうが、ある程度の成長なり維新が続く限り、長期的に人が余るということはないんじゃないか」と指摘する。鈴木氏は、高度成長期に工場で勤務していた時代を振り返り「当時300mくらいの組み立てラインで女性が働いていたが、技術が進み1人もいなくなった。当時は地方から集団就職で多くの人々が職を求めて上京していたが、それも今はほとんどなくなった。この現在で余剰人員があるかといえば、そういうことはない」と説明。アジア各国で人口減少が進むなかで経済成長が必須となるなら、余剰人員という問題は起こらないのではないかとした。
鈴木氏は「ただ、たくさん長生きすると、ちょっとその辺はわからないが……」としながらも「高齢者がより働けるような形のAIがあれば、非常におもしろくなるだろう」との考えを示した。
日本政府のAI政策について鈴木氏は「先頃中国から軽量のAI(DeepSeekと思われる)が出てきた。米国のAIは数十兆などかかっているが、中国の物はそこまで費用がかかっていないと思う。(こういう発明ができる)頭のいい人を大切に尊重する政策をやれば、AI政策も変わるのではないか」と持論を展開。
また、海外で進むクラウドサービスの展開について「米国の企業は毎年数兆円規模で投資する。これにわずかな投資で競争できるのか」と指摘。一方で、「運用は上手い」とIIJ自身を評価し、特殊なクラウドであれば競争できるとした。日本政府に対しても「日本のクラウド導入にあたっては、世界でもおもしろい運用の仕方、というところに政府が集中してやればいいのではないか」とそれぞれの国の状態や長所を活かした政策にすべきだとした。