ケータイ用語の基礎知識
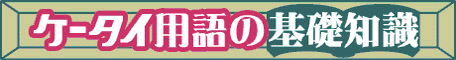
第784回:NOMA とは
2016年12月6日 06:00
より多くの端末で同時に通信ができる、5G以降の新通信コンセプト
LTE、LTE-Advancedといった4G(第4世代)方式のモバイル通信技術から、次の世代の技術にあたる5G(第5世代)では、さらに高速な通信速度などを実現するため、さまざまな技術が開発されています。
今回紹介する「NOMA」は、そんな5G以降で採用されるであろう無線通信の考え方のひとつで、「非直交多元接続」を意味する英語“Non-orthogonal Multiple Access”の略です。
NOMAの「MA」(Multiple Access)は、多元接続という意味です。これは、複数の電波(無線機)を使って通信する機器が、帯域をシェアして情報を送ることです。たとえば3G方式の携帯電話で採用された通信方式の「CDMA」は、CD(符号分割、Code Division)のMA、つまり(拡散)符号で分割したMAですし、PHSやTD-LTEなどの「TDMA」はTD(Time Division)、つまり時間で分割したMAです。
「同じ空間で複数の電波をやり取りする」という技術を工夫すれば、従来よりも効率よく、同じ空間に多くの端末を詰め込める、つまり効率よく帯域を使えるようになります。
NOMAは、簡単に言うと、これまでの考え方であった信号と更新する通信機器の直交性を崩すことで、これまでよりも効率よく、同じ空間で多くのデータ通信する端末を詰め込めるという多元接続の手法です。これまでの多くのMAは、直交多元接続と言い、複数のキャリア伝送において、ひとつのサブバンドに1ユーザーが割り当てられ、ユーザー同士で干渉が生じないようになっていました。NOMAでは、あえて干渉させてもよいと考えることでより多くの端末をセルに収容できるようにするのです。
しかし「直交性を崩す」とはどういうことでしょうか?
NOMAの「非直交」とは
直交とは、算数では「直角に交わること」と教わります。しかし、今回は情報科学における「直交性」というワードになります。これは「順引きでも逆引きでも、あるいは多次元的にも引く(探す)ことができる」ことを言います。
たとえば
「1→A」
「2→B」
という規則があるときに
「A→1」
「B→2」
あるいは
「1の次が2であるとき、Aの次がBである」
「Aの次がBであるとき、1の次が2である」
ということも同時に導き出せることを「直交性が高い」と言います。
これまでのCDMAやTDMAといった直交多元接続では、たとえば同じセル内で同じ周波数・同じ時間であれば、そこで通信している携帯電話は1台だけしかありませんでした。逆に、携帯電話と時間を特定すれば使っている周波数も特定できる、つまり“直交性があった”わけです。
これに対して、非直交なNOMAでは、この規則性を崩します。簡単に言うと、
「1→A」
「2→B」
が成り立つのに
「A→1」
「A→2」
が同時に成り立つのです。
実際の通信ではどうなっているかと言うと、たとえば、直交性のある多重接続のひとつである「TDMA」の場合、同じ空間にある複数の端末は、同じ周波数帯を使って通信しますが、その通信する時間が異なります。「Time Division」つまり、時間で分割されるわけです。
「基地局から端末Aへの通信 → 時刻 0」
「基地局から端末Bへの通信 → 時刻 1」
「基地局から端末Aへの通信 → 時刻 2」
という具合になります。
こうした考え方の“直交性のある通信”に対して、非直交な多重接続であるNOMAでは、ユーザー間で干渉してもいい形にしています。複数の端末で、同じ電波をつかったり、同じ時間で使っていても気にしなくて良いことにします。
ただ干渉がそのままであれば、通信しても内容が伝わりません。非直交な多重接続を実現するためには、たとえばSIC(Successive Interference Cancellation:逐次干渉キャンセル)という技術を利用します。これは、同じ時刻、同じ周波数で送られた信号の中から自分宛の信号だけを分離する技術です。
たとえば、基地局からごく近い端末と、とても遠い端末の2台があるとします。基地局~近い端末には、小さな出力の電波を、遠くの端末には大きな出力の電波を使いつつ、どちらも混ぜて信号を送ります。基地局から近い場所にいる端末にとって、遠い場所に向けて発射される電波が強いためわかりやすく、干渉対象としてキャンセルして、出力の小さい電波の信号のみを取り出します。
実際の通信では、様々な制約により、単純に簡単に通信速度が倍になるわけではないですが、周波数利用の効率化という意味では、NOMAは5G以降の通信では非常に重要なコンセプトであると考えられています。
