ケータイ用語の基礎知識
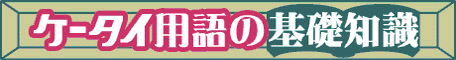
第720回:ジオフェンシング とは
(2015/8/18 08:00)
位置情報を使って仮想のフェンスを
ジオフェンシングとは、仮想的なフェンス(柵)を作る仕組みのことです。英語で書くと「Geofencing」となります。GPSやWi-Fi、ビーコンなどで取得できる位置情報を使って、利用者がこのフェンスで囲まれた領域に入った、あるいは囲いから出たことを判定し、このイベント情報をきっかけにコンテンツを表示したり、通知を行ったりします。
スマートフォンを持っているユーザーの現在地にあわせて、あらかじめ指定されたエリア(囲いの中)に入った場合、その近くにある店の情報など最適な情報を配信できます。そのため、いわゆるO2O(Online to Offline)と呼ばれる分野、つまり、ネット上(オンライン)での情報接触から実店舗(オフライン)への行動を促す施策として、商業上の利用がよくされます。
よくある例としては、ある店舗に近づくとスマートフォンに割引クーポンが届く、あるいは店舗内では売り場ごとにフェンスを張り、おすすめの商品を表示したりというような使い方ができます。
顧客の属性にあわせた配信
ジオフェンシングを使ったスマートフォンへの情報配信の実例としては、たとえば、2012年~2013年にかけてビックカメラが行っていた「ビック・スマートクーポン」の試験配信が挙げられます。この実験では、ポイントカードを持っているユーザーが、専用スマホアプリを使うと、ビックカメラ入店時にクーポンが配信されるというものでした。
配信対象となるユーザーは特定の条件を満たす必要がありました。たとえば、特定の売り場に5分以上滞在しているユーザーには、その売り場のおすすめ商品の割引や、ポイントアップを受けられるといった案内があったり、ユーザーのポイントカードの履歴から、過去の買い物に関連する商品、たとえば、買い替え時期に来ている商品や消耗品などに対応したクーポンを配信したりするといったものです。翌日の降水確率に合わせて「雨の日限定ポイントアップ」クーポンも配信されました。
店舗にとってはクーポンの配信だけではなく、ユーザーの滞在時間を測定することも可能になります。
ほぼすべてのスマホが対応
ジオフェンシングは、以前かiOSやAndroidで、標準的にサポートされています。たとえば、iPhoneなどの搭載されているiOSではiOS 5以降から、Androidではバージョン2.3(APIレベル9)からGPSを使ったジオフェンシングによるユーザーのモニタリングに対応しています。現在使われているスマートフォンならばほぼ対応可能であると言ってもいいでしょう。
ジオフェンシングを使ったサービスを作る場合、たとえば、AndroidでGPSを使ったおおまかな位置情報によるフェンシングを行うのであれば、Googleが公開している「Creating and Monitoring Geofences」というWebサイトを参考にすれば開発できます。
日本で、正確な位置情報を使ってジオフェンシングをしたいのであれば、NTTドコモが公開している「ジオフェンシングAPI」を使うこともできます。これは、ドコモが2015年6月に公開をし始めたAPIです。GPSや、駅などに配置されているドコモのWi-Fiスポットの位置情報を利用して、駅構内に入った、あるいは出たというような情報を得ることができるというものです。
ドコモのジオフェンシングでは、ドコモが提供するジオポイントに加えて、5ポイントまで任意の場所に設置できるトライアルキットも配布されています。これを利用することで、特定のエリアに仮想的なフェンスを作ることも可能になっています。
