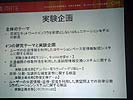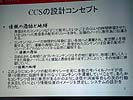| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KDDIは、2005年万国博覧会協会からの委託事業として、「愛・地球博」会場内において、企業や大学らとともにハイブリッド情報端末「愛・MATE」(アイ・メイト)を使ったP2Pなどを用いた共同実証実験を開始した。8日、「愛・地球博」会場内において、その概要説明およびいくつかの実験が行なわれた。 「愛・MATE」は、無線LAN機能およびCDMA2000 1xEV-DO方式に対応し、OSにWindows Mobileを採用した富士通製の携帯電話型情報端末。愛・地球博の会場では、愛・MATEを使って、通話、メール、ブラウザ、および電子ガイドマップなどが利用可能なほか、博覧会スタッフ向けの端末では、来場者への情報ガイドとして採用されている。 今回の実証実験には、京セラコミュニケーションシステム(KCCS)や、慶應義塾大学SFC研究所、名古屋工業大学らが参加。愛・MATEを使って、ユビキタス社会に向けた実験を行なう。実験には、名古屋地域の大学生や、ボーイスカウト、スポンサー企業のスタッフなど、のべ800人以上が参加するという。
■ 名工大、P2P上での宝探しゲームを実験
今回の実験では、会場内の日本広場に15台の親端末を配置し、3チーム各5端末の子端末を使って実験会場にバーチャルに浮かぶ“お宝”を探す。子端末には地図が表示され、画面上で指定された場所に行くと、親端末から個々の端末に文字が配信される。チーム5人それぞれが別の文字列を取得し、5人の文字を組み変えることで宝の場所がわかる仕組み。指示された場所にそれぞれ集まって、愛・地球博のキャラクター「モリゾー」と「キッコロ」の画像が表示されればゲームクリアとなる。メンバーの位置は、点在する親端末の電波強度によって、GPS機能がなくとも把握できる。また、表示される文字を元に特定の場所を見つける際には、メンバー5人とチャットで情報交換を行なう。 なお、各端末は、アクセスポイントを必要としない無線端末間のみで構成される「アドホックネットワーク」上にあり、離れた場所にいるチームのメンバーとチャットをする際には、アドホックネットワーク上の端末を中継して相互接続する「マルチポップネットワーク」が採用されている。 ただし、マルチポップ方式によるチャットでは、同じ無線通信機器でチャットの傍受が可能で、他の端末を経由することで、成りすましもできてしまう。このため今回の実験では、別途用意された認証サーバーで、親端末、子端末の証明を行なう。暗号鍵はあらかじめ端末に格納されており、証明された端末同士で暗号通信を行なうことでセキュアなチャットを実現している。
■ 慶応SFC、P2Pモバイル端末のコミュニケーションの可能性を探る
「ototonari」では、4つに分割したエリアにそれぞれジャンルの異なる音楽が潜んでおり、参加者がそのエリアに入ると端末固有の音源を獲得できる。獲得した音源は端末同士が近づくことで互いに分け合える。これを繰り返すことで8トラックの音楽が作成可能。作成した音楽は、各エリアに設置された端末に残しておける。別のエリアに行くと、他の人が作成した音楽を確認できる楽しみもある。 CCSは、「噂やクチコミを通信技術で実現する」としており、例えば今回のototonariのような仕組みを映画館などで導入すれば、情報をそのエリアに置いておくことで、次にその映画館に訪れたユーザーに対して、クチコミ情報を配信することができるという。 なお、SFC研究所では、愛・地球博会期中に、このほか3つの実証実験も行なう。1つは、愛・地球会場内の交通手段として導入されている自転車タクシーに愛・MATEを搭載し、遠隔地に写真画像を届けてもらうというもの。「デリバリー写ラウンド」と題したこの実験では、遠隔地のネットワーク環境の整備されていない地域において、日常の交通手段である電車やバスといったものにデータを運ばせて、遠隔地とコミュニケーションを行なうことが想定されている。 「モリゾー、キッコロを探せ!」という実験企画では、愛・MATEで撮影した画像をP2Pで周囲に配信し、周囲の人たちの滞留によって写真がその場に残される。そして、この残されたデータが次に訪れた人の手に渡り、バーチャルな写真館を実現するというもの。このシステムを応用して、例えば災害時の行方不明者情報などをアドホックネットワーク上で提供できるという。「野菜交換ゲーム」では、地域通貨のような電子補完通貨システム「iWAT」を利用して、P2Pで野菜を売り、その対価としてiWATを提供し、野菜を売った相手がさらに野菜を売っていくことで、P2Pで地域通貨を成り立たせていく実験が行なわれる。こちらも災害時の一時的な地域通貨などとして有効な仕組みとしている。
■ KCCS、無線LANと1xEV-DOのVoIPハンドオーバー実験
アクセスポイントとして、愛・MATEを数機種立て、参加者がアクセスポイント間をハンドオーバーしながらVoIPによる音声通話を実施。混雑する会場内では音声にノイズがのってしまう場合も多く、参加する若い女性に感想を聞くと、携帯電話より音声品質が悪いことに不満を漏らしていた。ただし、少し混雑が緩和されると、ノイズは解消されていた。 続いて、無線LANと1xEV-DOとのVoIPハンドオーバーの実験も行なわれた。こちらの実験には参加させてもらった。無線LANエリアから離れると、自動的に1xEV-DOへと切り替わるが、通常の通話時には、どこで切り替わったのかわからないほどスムーズにネットワークが切り替わった印象だ。ただし、実験参加時には、1x-EV-DOから無線LANのネットワークに切り替わる際に若干のタイムラグがあったことを加えておく。KCCSでは、将来を見据えた音声通話の1つの方法として今回の実験を行なった。現状、KDDIでは、1xEV-DO上でのVoIPサービスを提供していないが、今年3月のCTIA Wireless 2005では、クアルコムが1xEV-DO上でのVoIPサービスのデモンストレーションを行なっている。
■ URL 愛・地球博 http://www.expo2005.or.jp/jp/ KDDI http://www.kddi.com/ ■ 関連記事 ・ 愛・地球博会場で「愛・MATE」を使った実証実験 ・ ハイブリッド情報端末「愛・MATE」 ・ クアルコム、1xEV-DO上でのVoIPやRev.Aのデモ (津田 啓夢) 2005/07/08 23:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|